エンジニアをうまく採用できない理由と対策
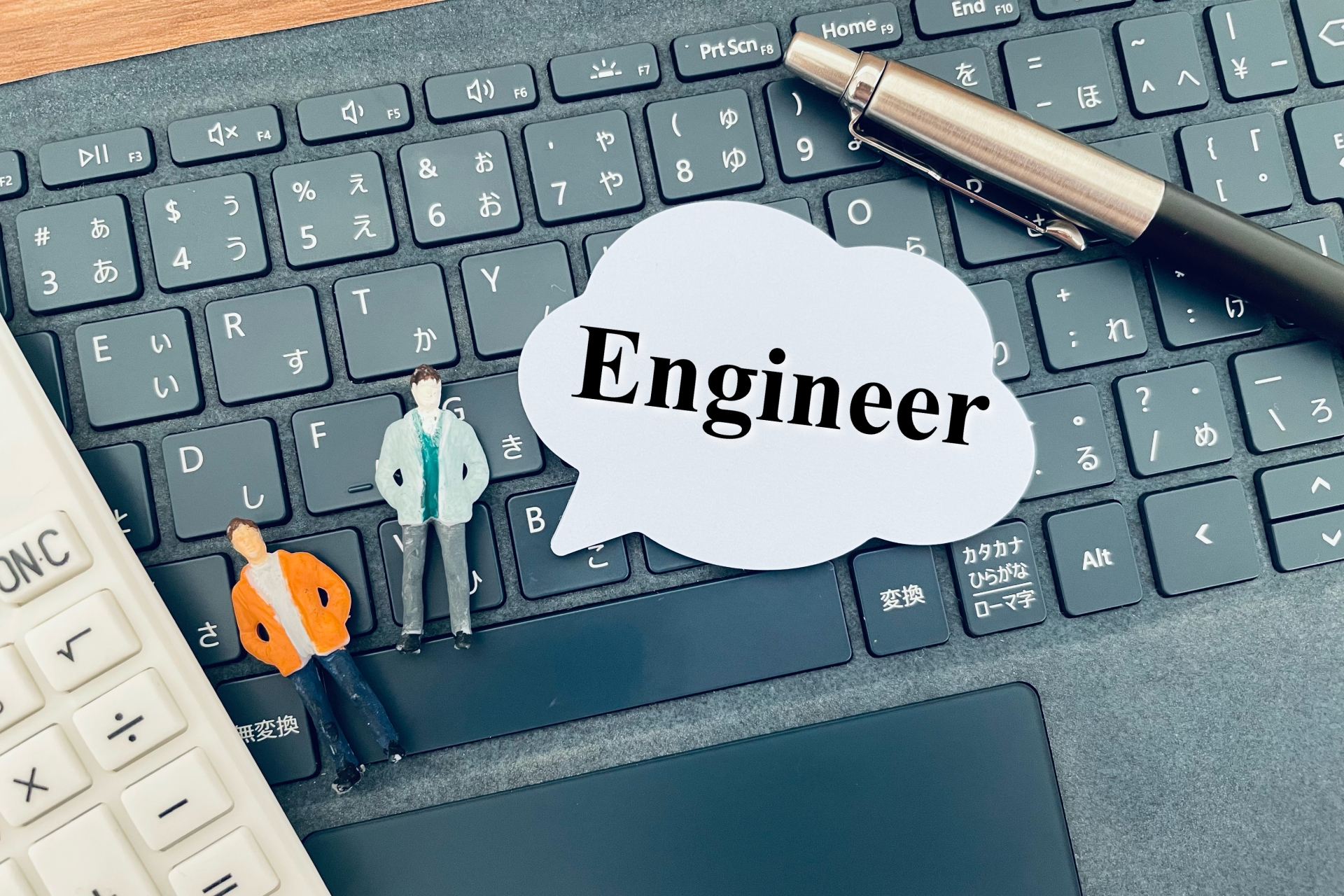
エンジニア採用は他職種と比べて特に難しいとされています。市場規模が拡大する一方、人手不足が深刻な課題であり、多くの企業がエンジニア採用に苦戦しているでしょう。
この記事では、エンジニアをうまく採用できない理由と、それに伴う改善策を解説します。エンジニア採用に課題を感じている方や企業は、ぜひ参考にしてください。
エンジニアを採用できない場合、新卒採用を専門家に任せるという手もあります。株式会社ABABAは、企業が新卒をスカウトするシステムをリリースしています。興味がある方はご覧ください。
エンジニアを採用できない状況とは
エンジニアを採用できない、またはエンジニアの採用がうまくいかない場合、以下のような状況のケースがほとんどです。
- 応募数が少ない
- 内定に結びつかない
- 内定を辞退される
- 早期に退職される
それぞれの状況について詳しく解説します。
応募数が少ない
求人を出しても、なかなか求人媒体からの応募がないケースは珍しくありません。また、最近では、企業側からアプローチすることや、人材紹介サービスを利用するケースも増えました。しかし、スカウトメールへの反応がない、人材紹介が来ないなどの状況に悩む企業も少なくありません。
応募がなかなか集まらない理由として、以下が考えられます。
- 認知・アピールが足りない
- 母集団形成ができていない
- 人材と接触する機会が少ない
特に、エンジニアは需要に対して応募者は足りていません。競争率が高いため、認知度の向上や自社にはない魅力のアピールが重要です。
内定に結びつかない
応募は来ても、内定に結びつかないこともあります。これは、スキルが不十分で求める能力を持つ人材に出会えないことや、書類選考のミスが原因です。
エンジニアといっても、保有するスキルは一人ひとり違います。求人に業務内容を詳しく掲載すれば、どの程度のスキルが必要なのかが分かるため、求める能力を持つエンジニアの応募が増えます。
また、面接が遅かったり回数が多かったりすると、内定前に辞退されるケースが少なくありません。これは、面接を終える前に他社から内定をもらうためです。
内定を辞退される
内定を出しても、辞退されることがあります。これは、何かしらの理由で他社に流れることが原因です。
内定を辞退される理由はさまざまで、主な理由として以下が挙げられます
- 面接で技術的な説明がなく、関心を得られていない
- 動機づけできていない
- 内定後のフォローアップが不十分
特に、内定後は定期的にコミュニケーションをとるフォローが大切です。特に新卒は、内定から入社までに時間が空くことは多いため、内定者フォローをして自社への信頼や入社意欲を高めましょう。
早期に退職される
入社しても3〜5年程度で辞めてしまうことに悩む企業も少なくありません。
エンジニア人材が定着しない主な理由は以下の通りです。
- スキルや業務とのミスマッチ
- 業務フローへの不信感
- 待遇の悪さ
- 人間関係の問題
エンジニアは需要が高く、好待遇の求人が多い傾向です。そのため、待遇が悪いとより待遇のよい他社に流れてしまう可能性があります。
また、スキルや業務のミスマッチによる早期退職は、選考でスキルを適切に把握することで予防可能です。ミスマッチによる離職が多い場合は、採用活動を見直しましょう。
エンジニアの採用ができない理由|市場の問題
エンジニアの採用がうまくいかない理由に、IT技術者の需要拡大や競合の多さなどが挙げられる。
ここでは、Web業界の急速な発展に伴う市場の変化について説明するほか、エンジニアの採用ができないといわれる主な原因を解説します。
エンジニア採用における市場が変化している
ITやWeb業界の成長によって、エンジニアの需要が急速に拡大しています。しかし、供給が追いついておらず、人材不足が深刻化しています。
特に即戦力のエンジニアを確保するための競争が激化しており、企業間で人材の取り合いが顕著です。さらに、働き方の多様化によってフリーランスや副業エンジニアが増え、転職市場に出てこないことも採用の難易度を上げている原因のひとつです。
現場にネガティブなイメージがある
エンジニアの労働環境にネガティブなイメージを持つ人がいることも、志望者が減る原因です。
給与はよくても、労働環境が悪いと働き手が見つからなかったり、働き手が見つかってもすぐに辞めてしまったりします。
エンジニアは、クライアントから要望があった製品を納期までに作ることが仕事です。作業が予定通りに進むとは限らず、想定外の事態が発生しても納期は変わらないとなると、残業が増えることや休日出勤をすることもあります。
このような現場のネガティブなイメージを持たれることで、エンジニアをうまく採用できません。
エンジニアの流動性が低い
優秀なエンジニアは十分な待遇を与えられていることが多く、転職する動機は少ない傾向です。その結果、人の流動性が低くなり、求人を出してもよい人材に出会えないこともあります。
よい人材を確保するには、報酬や労働環境を改善することや、モチベーションを与える、向上心に訴えかけるなどの対策が求められます。人材確保のために、労働環境や報酬の見直しを行ってみましょう。
エンジニアの成長が追い付いていない
IT技術の発達スピードが速いため、企業が求める技術にエンジニアが追い付いていないことも理由のひとつです。
生成AIやRPA、IoTなどIT技術は日々進化しています。
その一方で、すべてのエンジニアがIT技術の発達スピードに付いていけるとは限りません。技術の伴うエンジニアを確保するためには、エンジニアの成長を促す施策も必要です。
自社の差別化ができていない
近年、IT技術者を求める会社や業界が大幅に増えたことに伴って、エンジニアを採用する企業が増加傾向にあります。そのような中で、自社の差別化ができていなければ、多くの会社に埋もれてしまい、エンジニアの採用がうまくいきません。
以下では、自社の差別化ができていない企業の特徴についてまとめています。
- 受け入れ体制の不備
- ターゲット要件が曖昧
受け入れ体制の不備の例として、社内制度や労働環境の用意ができていないことや福利厚生の水準が低いことなどが挙げられます。改善を行わなければ、内定辞退や入社後の早期離職が起こりやすい状況に陥ります。
また、自社に必要なスキルや経験などのターゲット要件が明確でなければ、エンジニアに対して適切な訴求ができないでしょう。
エンジニアの採用ができない理由|採用活動の問題
エンジニアの採用がうまくいかない原因を、採用活動の面から深堀りします。
採用まで至らない原因を洗い出すことで、課題を解決する糸口になります。
エンジニアが求める待遇と条件が高い
エンジニアの市場価値が上昇する中、特に中小企業では、エンジニアが求める高い給与や待遇条件を満たすことが難しいといえます。このため、優秀な人材を確保しようにも、応募者が内定を承諾しないケースが多発しています。
また、経営層の採用市場に対する理解不足も課題のひとつです。雇用条件の改善や魅力ある社内体制の整備が間に合わなければ、競争力が欠けてしまいます。そうすると、企業が求めるレベルの高いエンジニアの採用がますます困難になります。
採用担当者の知識が不足している
採用担当者のプログラミングに関する知識が不足していると、現場と選考を進める人の間にミスマッチが生じます。
例えば、特定のプログラミング言語や技術が必要であるにもかかわらず、採用担当者が理解していないと、適切な人材を採用できません。応募者のスキルを見極め、採用の精度を高めるためにも、採用担当者がプログラミングの知識を身につける必要があります。
情報提供が不十分である
エンジニア採用がうまくいかない理由として、応募者の知りたい情報が提供できていないケースがあげられます。
応募者は、条件面だけでなく、社風に対して共感や興味を得ることで面談や面接へ進むケースがあります。そのため、応募者への情報提供が不足していると、採用活動を地道に進めても採用まで至りにくいでしょう。
採用活動をする際は、以下の項目を参考にしてください。
- 事業内容を明確に記載する
- 待遇に関する記載を徹底する
- 事業へのビジョンをまとめ提示する
- 社員インタビューを通して仕事の進め方ややりがいを伝える
- 写真や動画を用いて求人コンテンツを拡充する
これらの情報を提供すると、採用の成功率が上がります。
自社分析やブランディングができていない
採用でなにを打ち出すか、企業のなにをアピールするか曖昧なことが原因となる場合もあります。
自社に合うエンジニアを採用するためには、採用戦略を立てておくことが大切です。なぜなら、採用戦略を立てていないと自社のアピールポイントが分からず、求めるエンジニア像が不明瞭となるためです。
採用活動を開始する前に、採用全体のコンセプトを決めて採用に関わる社員全員に周知しましょう。
求める人物像が不明確である
企業が求める人物像が不明確であると、適切な候補者の見極めが難しくなります。
特に、求めるスキルや人物像が曖昧だと、最終選考で意思決定が遅れ、優秀な人材を他社に奪われるリスクが高まります。
また、ターゲット像が不明確なままでは、求人広告や採用広報で適切なアピールができません。
これを防ぐには、必要なスキルや人物特性を明確にし、採用基準を統一することが重要です。
採用チャネルが適切でない
エンジニアの採用がうまくいかない場合、採用チャンネルの見直しをおすすめします。
さまざまな採用チャネルで自社の情報を多方面へ発信すると、応募者が増える可能性が高くなります。
以下の項目をもとに、自社のチャンネル選択が適切かどうかを確認しましょう。
- ひとつのチャンネルに頼っていないか
- 自社の求める人材が登録するチャンネルを使っているか
- 求人サイトにおけるアクセス数や応募数の分析をしているか
また、SNSを通じて自社の情報を提供しつつ、求人メディアで人材募集する方法もあげられます。効果を確かめながら改善を繰り返しましょう。
応募者のスキル評価が困難である
採用基準が不明瞭であることも原因のひとつです。
人事担当者が求めるものと現場のニーズにズレが生じることもあります。応募者が所持するスキルの評価を採用担当が正しく評価できないと、ミスマッチが生じて早期離職になりかねません。
採用活動を始める前に、人事担当者と現場の責任者が話し合い、採用基準を明確にしましょう。また、採用に関わる社員全員への採用基準の周知も必須です。基準が決まったら採用担当者全員に伝え、選考時にはそれに従うことを徹底しましょう。
従来型の求人応募に頼っている
近年、採用方法は多様化しています。しかし、従来のように求人媒体や自社サイトの求人ページなどの発信に留まっていると、なかなかよいエンジニアに巡り会えません。
最近では求人媒体への掲載や自社サイトの求人ページの発信だけではなく、複数の採用手法を組み合わせる企業が増えています。
また、人材紹介・エージェントにばかり頼っていることや、受身の採用に終始することもNGです。ダイレクトリクルーティングのようなスカウト手法と併用して、「攻め」と「待ち」の両方を活用しましょう。
求人票に問題がある
仕事内容やどのような環境下で仕事をするかなどが不明確だと、応募者がなかなか集まりません。求人票は、その会社で自分の働くイメージが湧くものであることも大切です。仕事内容を具体的に記載することや、働く場所の雰囲気や人数、男女比などを記載しましょう。
また、専門用語に間違いがあると会社への信頼性が薄れます。求人票に記載する際には、ダブルチェックやトリプルチェックを行い、専門用語の間違いや誤字脱字がないかを確認しましょう。
採用までの流れに無駄がある
採用までの流れに無駄があると、選考のステップが多くなり、判断に時間がかかります。その結果、応募者が「連絡が遅い=不採用」と不安になり、他社に流れるリスクが生じます。
また、連絡の遅い企業は信用できないとも思われるでしょう。
応募者のニーズに迅速に対応し、面接日程も柔軟に調整することで、採用の成功率を高められます。無駄な手順を省くだけでなく、迅速な対応とフローの見直しも重要です。
内定辞退が生じている
内定辞退が生じる原因として、企業側の対応不足やミスマッチがあげられます。
内定提示後のフォローが不十分であったり、他社よりも魅力がなかったりすると、複数の内定を受けている優秀なエンジニアは他社へと流れます。また、スキルや業務内容のミスマッチ、社内風土への適応が難しいことも、内定辞退や早期離職の要因です。
面接時に応募者の志向性やスキルを詳細に確認して、適切にフォローをすることで、こうしたリスクを軽減できるでしょう。
入社後のキャリアパスが不明確である
エンジニアや理系人材にとって、入社後のキャリア形成の道筋が明確かどうかは、応募意欲や定着率を大きく左右する要素です。将来的な昇進や職種転換、スキルアップの可能性が見えないと「このまま働き続けて良いのか」という不安が強まり、特に優秀な人材ほど転職や早期離職を選びやすくなります。キャリアパスを提示できない企業は、結果的に人材の成長機会を制限してしまい、競合他社に流出するリスクを抱えやすいのが現実です。だからこそ、研修制度や評価基準、将来のロールモデルを具体的に示し、社員が自身の成長をイメージできる仕組みづくりが重要です。
採用マニュアルを整備していない
採用活動において明確なマニュアルや標準化されたフローが存在しないと、担当者や面接官ごとに判断基準や対応に差が出やすくなります。その結果、候補者に不公平感を与えたり、欲しい人材を正しく見極められず採用の質が下がったりします。さらに、ミスマッチによる早期離職や内定辞退の増加にも直結しかねません。選考過程のバラつきは候補者体験の低下につながり、企業の採用ブランドを損ねます。統一された基準や評価シートを準備すると、公平性と一貫性を担保でき、誰が担当しても同じ質で候補者と向き合える体制が整います。これにより採用効率と定着率が同時に改善されるのです。
本来求めるスキルや人柄を妥協している
採用競争の激化により、「とにかく人を入れたい」と基準を下げて採用してしまうと、結果的にスキルや価値観が噛み合わず、早期離職や職場の不和につながるリスクが高まります。
- 採用基準を曖昧にして数合わせを優先すると、ミスマッチを引き起こしやすい
- 本来必要なスキルや人柄を定義しないままでは、同じ失敗が繰り返される
- ミスマッチ人材が増えると教育・マネジメントコストも膨らみ、現場の負担が増大する
短期的には人手不足を補えても、長期的には組織力を削ぐ原因になります。だからこそ「必要な人材像を明確化し、妥協せず採用する」姿勢が不可欠です。しっかりと基準を策定し共有することで、安定した組織づくりと定着率向上につながります。
応募者との関係が対等ではない
採用活動において企業側が「選ぶ立場」という一方的な姿勢を見せてしまうと、応募者は「見下されている」「柔軟性がない」と感じてしまいます。その結果、選考辞退や不信感につながる可能性があるため注意が必要です。特に技術職は売り手市場であり、企業が優位に立つという構図は通用しません。面接や面談の場では、応募者の意見や質問を尊重するフラットなコミュニケーションを意識することが大切です。また、双方向型の面接設計を取り入れることで信頼関係を築きやすくなり、応募者が「ここなら自分を理解してもらえる」と感じやすくなります。結果的に、企業の魅力を正しく伝えられ、採用成果の向上にもつながります。
エンジニア採用を成功に導く対応策
エンジニア採用を成功させるには、エンジニアが自社に魅力を感じる必要があります。企業側からの積極的なアプローチや、魅力ある社内環境の整備などの対策をとりましょう。
ここからはエンジニア採用を成功に導く対応策について、7つ紹介します。
ビジョンに基づいたエンジニア採用計画を立案する
採用活動をする際は、初めに採用計画を立案します。この際、経営ビジョン・中長期の経営計画に連動して採用計画を立てましょう。なぜなら、経営ビジョンに基づいて採用立案を立てることで、将来の会社の成長に貢献するエンジニアを採用できるためです。
将来、自社の戦力として必要なエンジニア像を明確にしましょう。ターゲット・ペルソナを明確にして、必要な人材の計画的な採用が成功のコツです。
採用チャネルを精査する
ターゲットに合う採用チャネルを決めましょう。
現在、採用チャネルは求人媒体・自社サイト・人材紹介・ダイレクトリクルーティング・SNSなど、数多くの種類があります。どのチャネルでエンジニアにアプローチするかを精査します。
採用チャネルを選ぶ際は、自社とターゲットに合うチャネルを選ぶことが大切です。複数のチャネルを組み合わせて、自社が求めるエンジニアに出会える確率を上げましょう。
言語や開発環境を求人情報に掲載する
エンジニアが採用できない原因の1つに、求人情報の不明確さがあります。特に、開発言語やフレームワーク、使用ツールが記載されていないと、求職者は応募をためらう可能性が高まります。エンジニアは自身のスキルが活用できる環境を重視するため、技術スタックの具体的な記載が重要です。
また、開発プロセスやチーム構成を明示することで、求職者が働くイメージを持ちやすくなるでしょう。詳細情報の掲載によって、適切なスキルを持つ人材の応募が増え、採用成功率が向上します。
エンジニアにとっての自社の魅力を明確にする
競争率の高いエンジニアに自社を選んでもらうためには、他社にはない魅力を伝えます。
競合他社と比較して、自社にはどのような強みや魅力があるのかを明確にします。自社のエンジニアが、会社に対して感じたメリットについてインタビュー収集する方法もおすすめです。
エンジニアに求める条件をはっきりさせることも大切です。求人票が分かりやすく、条件や業務内容がはっきりすると、自社への応募意欲を高められます。
エンジニアにとっての自社の魅力を明確にして、求人や選考でアピールしましょう。
オウンドメディアでエンジニア向けコンテンツを発信する
自社サイトやブログなどのオウンドメディア・SNSがある場合は、オウンドメディア・SNSなどを活用する方法もあります。特に、SNSは新卒世代が日常的に利用するため、自社に興味を持ってもらうきっかけにつながります。
新卒獲得を目指す際は、エンジニアを目指す学生向けコンテンツの発信をしましょう。併せて「エンジニアを大切にする会社」という印象を与えることで、入社意欲を高められます。
最新技術を導入する
企業がAIやブロックチェーンといった最新技術を積極的に導入していない場合、応募者から「成長機会が少ない」「技術的な魅力に欠ける」と受け止められるでしょう。特にエンジニアは、自分のスキルを高められる環境や新しい技術に挑戦できる現場を求める傾向が強いため、導入の有無が志望度に直結します。一方で、最新技術を取り入れることで「学習意欲の高い人材が集まる環境」として認識されやすく、意欲的なエンジニアからの応募が増える可能性があります。さらに、企業ブランドの向上や採用活動の成功率アップにもつながるため、積極的な技術導入は採用戦略の一環として重要です。
採用側の知識を強化する
エンジニアは非常に多くの能力が求められる職種です。応募者を単純な開発スキルや言語、実績のみで判断することは避けましょう。
応募者のスキルを把握するには、採用側にもある程度の知識が必要です。自社が求めるエンジニア像を把握して、それに応じた言語の種類や利用目的について学びましょう。
また、エンジニアの種類や役割に関する知識も欠かせません。
人事や採用担当者が、エンジニア業界における必要最低限の知識・常識をおさえれば、入社後のミスマッチを防げます。
現場のエンジニアに協力を求める
エンジニアを募集する場合、面接に現場のエンジニアを参加させることでミスマッチを防ぎ、応募者の信頼獲得につながります。
前述の通り、人事担当者と現場のニーズは違うことがあります。採用基準を設けるとともに、現場のエンジニアに面接へ参加してもらうことで、ミスマッチの防止が可能です。また、面接の内容も一緒に考えてもらうこともおすすめです。
現場のエンジニアには繁忙期があるため、早めに面接の日程を決めて可能な限り面接に参加してもらいましょう。
CTOと連携する
エンジニアの採用を成功させるには、技術的な視点を踏まえた選考が不可欠です。ニアが採用できないと悩む企業は、CTOとの連携強化で、求職者のスキルを的確に評価でき、実務に即した質問の用意も可能です。
また、CTOが直接求職者と対話することで、企業の技術的な強みや魅力を伝えやすくなり、優秀なエンジニアの関心が引けるでしょう。さらに、面談を通じてCTOと求職者の相性を確認できるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
求めるスキルを明らかにする
エンジニア採用においては、自社に不足しているスキルや求める人材像の明確化が不可欠です。
現場エンジニアからヒアリングし、必要なスキルや経験を具体化しましょう。採用プロセスに反映させることで、適切な人材のマッチングができます。面接時には、現場のエンジニアも参加させて、応募者との相性確認もしてください。
さらに、経営陣と相談を行い、採用活動に集中できる環境を整え、リソースを確保することも求められます。
選考プロセスを適切なものにする
応募者は複数の求人に応募するため、企業は迅速かつ真摯な対応が求められます。連絡が遅れると「信用できない」とみなされ、他社に優秀な人材を奪われるリスクが高まります。
選考スピードの向上・候補者への速やかな返信・オンライン面談・評価基準の明確化など、効率的なプロセスの構築が重要です。
また、複数の採用手法を組み合わせることで、より多くの候補者にアプローチできるでしょう。
職場環境と条件をアピールする
求職者から選ばれない要因には、自社の魅力が伝わらない、候補者体験が悪いなどがあります。
そこで、自社の魅力や強みを明文化し、ターゲットとなる候補者へ提示しましょう。ノー残業デーの導入やキャリア相談体制の整備など、社内環境や制度を整えることも重要です。
競合と差別化できる条件を提示し、職場環境の魅力と強みをアピールしましょう。
ダイレクトリクルーティングや外注を利用する
ダイレクトリクルーティングや外部の採用アウトソーシングサービスを活用することで、エンジニア採用の効率を高められます。専門知識が求められるエンジニア採用においては、プロからの視点やアドバイスを得ることで、精度の高いマッチングが可能です。
また、エージェントを利用しても成果が上がらない場合は、原因を探り、要件や訴求点の見直しをすることが重要です。こうしたアプローチによって、社内での手間や工数を減らしつつ、効果的な採用活動が実現します。
ミートアップを企画する
ミートアップの開催もおすすめです。なぜなら、ミートアップを開催することで、お互いを知れるためです。
例えば、企業側は自社に合う学生やエンジニアを見つけられます。一方学生側も、自分に合う企業を見つけられたり、知りたい情報を収集できたりするなどのメリットがあります。
中小企業は、ミートアップを開催することで学生に自社のことを知ってもらえるため、認知度の向上が可能です。
面接で動機付けを行う
「スキルアップを目指したい」や「働く場所や時間にとらわれたくない」など、応募者の志向はさまざまです。そのため、応募者の志向を聞き出し、それに合わせたメリットや目標を提示することで、入社後のミスマッチを防げます。
面接では、志望動機を丁寧にヒアリングしましょう。その上で、自社で働くメリットを伝えます。応募者に合わせた対応が成功のコツです。
内定通知に付加価値を持たせる
エンジニアが採用できない問題を解決するには、内定通知の出し方にも工夫が必要です。単なる結果通知ではなく、歓迎メッセージや内定の決め手を伝えることで、企業の温かみを伝えられます。
さらに、入社後のキャリアパスや成長支援制度の提示によって、求職者が将来のビジョンを描きやすくなるでしょう。このような取り組みをすることで、内定辞退の防止や、入社後の定着率向上につなげられます。
内定から入社までのフォロー体制を整える
内定から入社までのフォロー体制を整えることは、入社辞退を防ぐだけでなく、離職率を下げることにも役立ちます。
内定後、候補者は慎重になりやすく、新たな懸念が生じることも多いといえます。
フォローにおいては、密なコミュニケーションが欠かせません。例えば、入社前に職場体験をすると不安を解消できるでしょう。また、現場社員との食事会や懇談会も効果的です。
入社後のフォローアップを行う
新卒は、エンジニアとしての経験や実績がほぼありません。そのため、入社後は丁寧なフォローアップが大切です。
新人教育を実施したり、エンジニアが業務に集中しやすい環境を整備したりするなど、早く職場に慣れるためのサポートをしましょう。
働き方の多様化、学習環境の提供、キャリアアップのプランの明確化なども、入社後のモチベーションの維持または向上に役立ちます。
エンジニア採用ができない企業と成功する企業の違い
エンジニア採用に苦戦する企業と成功する企業を比較すると、多角的な要素が影響しています。採用戦略や社風の伝え方、候補者への向き合い方など、企業がどの点を重視・整備しているかで、採用成果は大きく変わるのです。
母集団形成の違い
エンジニア採用がうまくいかない企業の多くは、採用ターゲットが不明確で、求人情報の開示も限定的です。そのため応募者が集まりにくく、母集団自体が形成されません。一方で成功する企業は、ペルソナを具体的に設定し、求めるスキルや人物像を明確化しています。また、ターゲット理解に基づいた選考プロセスの設計や、応募者の心理に寄り添った働きかけを行うと、適切かつ十分な候補者を集められるのです。結果として、採用成功率に大きな差が生まれます。
書類選考の違い
採用に苦戦する企業は、書類選考における評価基準が曖昧で、担当者ごとに見方が異なるため、一貫性を欠いてしまいます。その結果、本来評価すべきスキルや経験を持つ逸材を見逃し、選考の質が低下してしまうのです。一方で成功する企業は、書類だけで候補者を判断せず、オンライン面談やカジュアル面談を積極的に取り入れています。直接顔を合わせると人物像やポテンシャルを正しく評価できるため、適切な人材を逃さず採用につなげています。
面接日程調整の違い
採用に成功する企業は、応募者の予定を第一に考え、柔軟な日程調整を実施。例えば、平日の夜間や休日対応、オンライン面接の導入など、求職者が参加しやすい環境を整えています。一方で採用できない企業は、担当者のスケジュール都合を優先しがちです。求職者への面接案内が遅れる状況もあります。その結果、応募者の熱意が冷めたり、他社で先に内定が決まったりすると、面接前に辞退されてしまうケースが発生しやすいのです。柔軟さとスピード感の差が、成果を左右するでしょう。
面接の違い
採用に成功する企業は、面接を単なる選考ではなく「相互理解の場」として活用しています。例えば現場エンジニアが参加し、仕事内容や開発環境をリアルに伝えて応募者の不安を解消し、動機付けの時間を十分割いています。一方で、採用できない企業のうち面接担当者の専門性が不足しており、技術的な質問に答えられなければ解決すべき課題です。また、評価基準が曖昧だと、応募者に不信感を与えてしまいます。その結果「ここで働いて大丈夫だろうか」と不安が強まり、優秀な人材ほど他社へ流れてしまうのです。
内定の違い
採用に成功する企業は、内定を出した後も丁寧なフォローを欠かしません。具体的には、内定通知後に定期的な連絡を入れたり、経歴の近い社員との面談を設けたりして、不安解消や入社意欲の向上につなげています。これにより、応募者は「この会社は自分を大切にしてくれている」と感じ、安心して入社を決意しやすくなります。一方で、採用がうまくいかない企業は内定通知だけで満足してしまい、内定後のフォローが不足しがちです。その結果、不安が解消されず他社に流れてしまい、辞退率の高さにつながります。
「採用できない」から脱却する採用手法
採用できない状況を脱却するには、新たな施策の導入がおすすめです。
ここでは、多様化する採用手法を柔軟に取り入れるためのポイントを紹介します。採用後のミスマッチを防ぐほか、内定辞退を阻止する方法もあわせて解説するため、参考にしてください。
プロモーション
複数の求人媒体を活用し、効果的にプロモーションを行うと、自社が求めるエンジニアに出会える可能性が高まるでしょう。例えば、ブログやSNSに自社の採用ページを紐づけて多くの人にアプローチすることがあげられます。
ほかにも、エンジニアに特化したマッチングサイトの活用もおすすめです。
マッチングサイトにはそれぞれ特徴や魅力的なサービスがあります。自社の目的や状況に応じて最適なものを導入してください。
採用ピッチ資料の作成
エンジニアが採用できない状況の改善には、企業魅力の適切な伝え方が重要です。そのために有効なのが、採用ピッチ資料の作成です。これは、企業のビジョン・プロダクト・技術スタック・働く環境などを分かりやすくまとめた資料のことで、求職者が企業の技術力や成長性を理解する助けになるでしょう。
さらに、SNSやイベントでの配布によって、認知拡大にもつながります。エンジニアが興味を持つ情報を網羅した採用ピッチ資料の活用で、採用成功の可能性を高められます。
テックブログの運用
エンジニアの採用において、認知拡大とブランディングは非常に重要です。エンジニアが採用できないと悩む企業は、テックブログの運用がおすすめです。自社エンジニアが技術的な知見や開発事例の発信で、同業のエンジニアに興味を持ってもらいやすくなるでしょう。
また、企業の技術力や開発環境をアピールできるため、求職者の信頼を獲得できます。さらに、実際に働くエンジニアの声を伝えることで、求職者が職場環境を具体的にイメージしやすくなり、応募意欲の向上につながります。
採用方法の拡大
採用方法は一つではありません。従来の採用方法以外の方法を採用することも成功につながります。
参考として、採用方法には以下があります。
- リファラル採用:自社の社員から知人や友人を紹介してもらう採用方法
- ダイレクトリクルーティング:求職者データベースから人材を探して直接オファーをする採用方法
- ポテンシャル採用:応募者の過去の実績や経験ではなく、将来の成長やリーダーシップ、学習能力などの数年後の活躍を見込んで採用する方法
カジュアル面談の実施
エンジニア採用では、求職者との接点を増やすことが重要です。エンジニアが採用できないと悩む企業は、カジュアル面談の積極的な実施が有効です。選考前に求職者と企業が気軽に対話できる場を設けることで、求職者は企業の雰囲気や開発環境を把握できます。
一方、企業側も求職者のスキルや志向を早期に理解できるため、ミスマッチを防ぐことが可能です。リラックスした雰囲気での交流によって、信頼関係を築きやすくなり、選考への前向きな意欲を引き出せるでしょう。
インターンの実施
エンジニアが採用できないと悩む企業は、インターン制度の活用が有効です。特に内定後に長期インターンの実施によって、求職者が入社前に職場環境や業務内容を体験でき、入社後のギャップを減らせます。
また、企業側も求職者の適性やスキルを事前に確認できるため、入社後の活躍を見越した採用が可能です。インターンを通じて社内のメンバーと関係を築くことで、内定辞退のリスクを低減できます。インターン制度を積極的に活用することで、より適切な人材を確保しやすくなるでしょう。
接点を増やす施策
SNSの活用や求人イベントへの参加で、求職者との接点を増やしましょう。
なかなかよい人材に巡り会えない場合は、接点を増やして応募者数を増やすことで選択肢が増えます。特にSNSは日常的に多くの人が利用しており、応募者も利用しやすいツールです。
また、書類だけで判断せずに積極的に面接をしましょう。なぜなら、直接会って会話をすることで、書類だけでは分からないポテンシャルや人柄が分かるためです。「会いたい人を選ぶ」のではなく、「会う必要がない人は選ばない」という思考に変えてみましょう。
外国人採用の検討
エンジニアが採用できない課題を解決するには、国内人材に限らず海外の優秀な人材採用の検討も有効です。海外のエンジニアは高い技術力を持つ即戦力となる可能性があり、採用の幅を広げられます。外国人採用の成功には、ビザ取得支援や社内の受け入れ体制の整備が不可欠です。
また、文化の違いを理解し、多様性を尊重する職場環境を作ることで、円滑なコミュニケーションを実現できます。さらに、日本国内にいる外国人エンジニアをターゲットにした採用活動で、採用成功率を高められます。
多様な雇用契約形態の導入
エンジニアを採用できない原因の1つとして、雇用形態の選択肢が少ないことも挙げられます。フルタイム正社員だけでなく、契約社員・業務委託・フリーランス・副業人材など、多様な雇用形態の導入によって、より多くの人材を確保しやすくなるでしょう。
特に、高スキルのエンジニアはプロジェクト単位で働くことを希望するケースも多いため、柔軟な契約形態の提示で採用の可能性が広がります。また、社内のリソース状況に応じて必要なタイミングで適切な人材を確保できるため、採用活動の効率化にもつながります。
柔軟な勤務形態の導入
エンジニアが採用できない課題の解決には、柔軟な働き方の導入が効果的です。リモートワークやフレックスタイム制を採用することで、求職者にとって魅力的な職場環境を提供できます。特に、通勤時間を削減したいと考えるエンジニアにとって、リモートワークの導入は応募のハードルを下げる要因となり得ます。
また、フレックスタイム制を活用することで、エンジニアが最も生産性の高い時間帯に働け、成果を最大化しやすくなるでしょう。副業やパートタイム勤務を認めることで、多様な人材の確保も可能です。
理系特化ではない媒体を使う
理系採用だからといって必ずしも理系特化型の媒体に限定する必要はありません。あえて理系特化ではない媒体を利用すると、幅広い層にリーチでき、思わぬ優秀層と出会える可能性があります。ただし利用を検討する際には、ターゲットとなる理系学生のボリュームを事前に確認しておくことが重要です。「ABABA」は最終面接経験者に限定してスカウトできるサービスで、効率的に理系学生へアプローチできます。実際にABABAを使って、機械・電気・情報系学生の採用に成功した事例もあります。結果としてミスマッチを防ぎつつ、内定承諾率の高い母集団形成を実現できる点が大きな魅力です。
まとめ
エンジニア採用ができない原因には、競争の激化や採用フローにおける課題などがあります。
採用を成功させるためには、エンジニアの視点を重視し、積極的なアプローチと魅力的な社内環境の整備が不可欠です。企業には、エンジニアが求める条件や成長機会の提供、技術面でのサポートが求められます。
また、迅速な選考プロセスや効果的な内定者フォローなど、採用の各段階での工夫が成功の鍵です。
エンジニアの採用には、外部採用サービスの活用も効果的です。株式会社ABABAは、独自のスカウト機能や学歴に偏らない候補者選定、不採用者との良縁を保つ「お祈りエール」などの独自の手法を持ちます。ABABAでは、就活生がどの企業の選考を進んでいるかが可視化され、自社の求める人材とマッチしているかの判断が可能です。そのため、採用者の知識不足を補い、スキルや待遇などのミスマッチを防ぐことにつながります。
エンジニア採用の手段として、ABABAの提供するサービスをご活用ください。
◆ABABAの特徴
| ・ライバル企業の最終面接を受けた優秀な人材に対してアプローチできる ・同業他社を志望している就活生であれば、希望業界や思考性に共通する部分もあり、無駄なく効率的にスカウトができる ・優秀で自社にマッチするエンジニアの採用を、無駄なく確実に実現できる |
ABABAを利用する企業から、就活生に向けた100万を超えるスカウトが生まれ、67%という高い内定承諾率を誇ります。
サービスについてはこちらをご覧ください。
また、新卒採用を成功させるには戦略が重要です。
お役立ち資料では「新卒採用後半戦の戦略」を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
杉原 航輝(株式会社ABABA 執行役員)
新卒・中途採用領域を中心に、法人向けの採用支援や採用コンサルティングを経験。ダイレクトリクルーティングを含む採用戦略設計から実行支援まで携わる。
また、新卒採用における内定者フォローや採用定着を目的とした施策設計・立ち上げにも従事。
2023年より株式会社ABABAに参画し、執行役員としてマーケティングおよびインサイドセールスを管掌。












