新卒が内定辞退する理由とは?企業ができる対策を解説
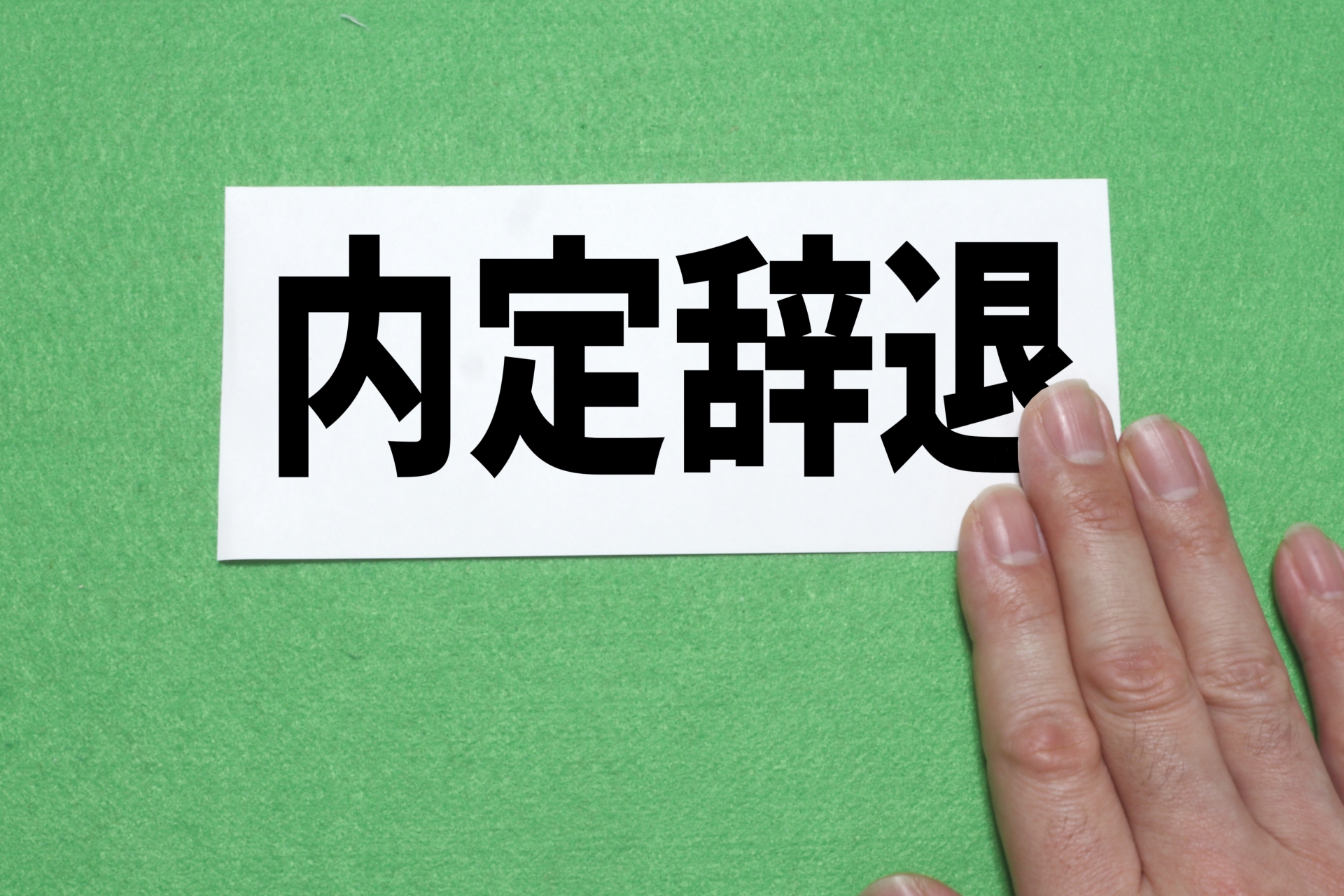
企業は採用業務には多くの労力と費用がかかるため、内定辞退は避けたい事態です。その一方で、学生は複数の会社の採用を受けることで内定辞退をする可能性があります。
そこで今回は、新卒が内定辞退をする理由や企業ができる対策をご紹介します。
新卒スカウトサービスABABAは、内定承諾率業界No.1を誇るサービスです。内定辞退にお悩みの際は、ABABAの活用がおすすめです。興味のある方は、ぜひ以下の資料もご覧ください。
新卒の内定辞退の現状
新卒の内定辞退に悩む企業は少なくありません。
株式会社リクルートが調査した結果によると、2023年と2022年の新卒者のうち2人に1人は内定辞退をしたことが分かります。また、学生側の調査結果を見ると6割が1社以上から内定を受けており、平均で3.4社を辞退しています。
このように、新卒者が内定辞退をする確率は高く、多くの企業が内定辞退に悩んでいる状況です。
新卒が内定辞退を決断する理由
内定辞退を防ぐためには、内定辞退をする理由の把握が大切です。
新卒が内定辞退を決断する理由はさまざまです。そのなかでも特に多い理由として、以下が挙げられます。
- 他社により魅力を感じた
- 志望時点でのイメージと実際が異なっている
- 価値観が合わない
- 会社の悪い噂を聞いた
- 会社の将来性に不安がある
- 新卒側の事情が変わった
それぞれの理由について詳しく解説します。
他社により魅力を感じた
複数社から内定をもらった新卒は、最も魅力に感じる企業を選びます。
例えば、中小企業より聞き馴染みのある大手企業の方が将来性や信頼性が高いと判断し、中小企業の内定は断る傾向です。他にも、より志望度の高い会社から内定をもらえると、他の企業の内定は辞退します。
中小企業でも自社の魅力を適切にアピールすることで、学生に選ばれる可能性は十分にあります。
志望時点のイメージと実際が異なっている
選考を受けてみて、イメージとギャップがあったことも理由となるケースもあります。
ギャップが生じる原因は、採用担当者や面接官の印象が悪い、社風が合わない、内定後への対応が悪いなどです。採用担当者や面接官、内定後の対応に問題がある場合は、担当者を変更してイメージアップを図りましょう。
価値観が合わない
価値観が合わないことも理由の一つです。価値観が合わないと感じる原因として、内定後に会社の社風や価値観に触れて「違う」と感じたり、接触した社員の印象から判断したりが挙げられます。また、就活をするなかで得たさまざまな情報から、価値観や捉え方が変わるケースもあります。
就活生自身の価値観が変わったことによる原因の場合は対応が困難です。しかし、内定後に価値観が合わないと感じさせることを避けるためには、選考や求人ページで社風を詳しく伝えることが大切です。
会社の悪い噂を聞いた
ブラック企業やパワハラ、経営が傾いているなど、会社の悪い噂を聞いたことで、内定自体を決断することもあります。
SNSや口コミサイトなどで噂を知ったものの、応募者はその情報が本当かを判断することはできません。また、「このような書き込みを見つけましたが本当ですか」と会社に直接確認することはできないため、真偽が分からず不安を感じて内定を辞退するケースです。
SNSや口コミサイトの情報は全て正しいとは限りません。なかには選考に落ちた人が、腹いせで悪い噂を書くこともあります。しかし、悪い噂を見かけると、真実ではないことでも内定者は不安を感じます。
会社の将来性に不安がある
中小企業に多い理由として、会社の将来性に不安を感じることが挙げられます。例えば、「キャリアビジョンが描けない」「待遇がよくない」「会社が発展しそうにない」などは、会社の将来性に不安を感じる要素です。
長く勤めることを想定する内定者にとって、会社の将来性は重要です。会社に将来性があることをアピールしましょう。
新卒側の事情が変わった
親からの反対や進学・留年、介護や育児をすることになったなど、新卒側の事情が原因となるケースもあります。
これらのケースでは、企業側に問題があるわけではないため防ぎようがありません。しかし、将来再度志望してもらえる可能性もあるため、友好な関係を継続できるように内定辞退の受け入れをしましょう。
新卒の内定辞退が生じやすいタイミング
新卒が内定辞退をするタイミングはさまざまなものの、多くのケースで以下のタイミングに生じます。
・志望度の高い企業から内定を受けたとき
・内定承諾率書や契約書の締め切り間際
・内定式や内定フォローイベントの後
・入社前(1〜3月)
それぞれのタイミングで内定辞退が多い理由を解説します。
志望度の高い企業から内定を受けたとき
ほとんどの就活生は、複数の企業を受けています。通常、7〜9月頃に他社から内定を受けることもあり、内定を受けた企業のなかから最終的に選ぶ会社を決めるケースがほとんどです。この際、自社より志望度や好感度の高い企業があれば、その企業の内定を受けます。
自社の志望度や好感度を上げるためには、内定者フォローや自社の魅力のアピールなどが大切です。
内定承諾書や契約書の締め切り間際
2月頃になると、本命でない場合に辞退が起きやすい傾向にあります。これは、内定を迷っていたものの、締め切りが近くなり他の企業を選ぶケースです。また、場合によっては迷っていて時間切れになることもあります。
内定承諾書や契約書の締め切りが近づいていて、内定を受けていない場合は辞退する可能性が高いといえます。
内定式や内定フォローイベントの後
内定式や内定フォローイベントの後に辞退するケースも少なくありません。これは、内定式で「思っていたのと違う」と感じたり、集団の雰囲気に違和感を感じたりするためです。
内定者フォローをすることで、内定者の不安を解消したり信頼関係を構築できたりします。しかし、現場の人と話したり社内の雰囲気を見たりしたことで、内定者が思い描いていたイメージと異なると感じることがあります。
入社前(1〜3月)
1〜3月の入社直前に内定を辞退するケースもあります。入社直前に内定を辞退する理由は、主に以下の通りです。
・年末年始の帰省で親からダメ出しを受けた
・勤務地や配属先に同意できない、または気が進まない
・卒業できなかった
勤務地や配属先に不満が生じることを防ぐためには、内定時や選考時に希望を確認することや、あらかじめ伝えることが大切です。
内定辞退の理由に寄り添う考え方
内定辞退はなるべく避けたいも事態ではあるものの、どれだけ対策を行っても内定辞退をされることはあります。この際、辞退理由に寄り添う考え方を持つことが大切です。
ここでは、内定辞退の理由に寄り添う考え方をご紹介します。
内定者の心情に配慮する
丁寧な内定者フォローをして、不安を解消することで内定辞退を防げます。
例えば、内定を出したら定期的に連絡をしましょう。内定者が知りたい情報を提供することで、不安解消が可能です。
また、定期的な連絡や知りたい情報の提供は、志望度が低くても好感を持ってもらえる場合があります。好感度が上がれば、志望度が高い他の企業から内定が出ても、自社を選ぶ可能性が上がるでしょう。
自社も評価されていると考える
自社の内定を辞退して他社を選んだとなると、自社に問題があるのではと感じます。しかし、自社に魅力がないわけではなく、他社の方が内定者に合っていただけと考えましょう。
内定辞退をされると、「会社に優先順位を付けられた」「社風を悪く見られている」と思うでしょう。しかし、自社についてありのままに魅力や課題を正しく伝えたり、事業に対する真摯な姿勢を見せたりすることが大切です。
内定者に対して前向きな姿勢を維持することで、信頼度が上がって内定承諾率向上が期待できます。
新卒の内定辞退を防ぐための具体的な対策
新卒が内定辞退をする理由はさまざまあるものの、対策をすれば内定辞退を防げる可能性があります。そこでここからは、内定辞退を防ぐための施策をご紹介します。
原因を究明し、適切な対策を行うことで内定辞退を防ぎましょう。
コミュニケーションの強化
内定を出した後も定期的にコミュニケーションを取りましょう。なぜなら、内定から入社まで期間が空く場合、連絡が取れないと内定者は不安を感じるためです。
例えば、社内見学やインターンを実施すれば、所属先の雰囲気や人間関係、業務内容が分かります。これらが入社前に分かれば、不安の解消にもつながります。
また、社員や内定者同士で交流する場を設けることも有効です。入社前に共に働く人と交流できれば、人間関係の不安解消や円滑な業務遂行に必要な連携が取れます。
情報の提供
新卒が誤った情報を元に判断をしないように、正しい情報の提供を心がけましょう。
内定者は、内定を受けた企業の口コミや評判を確認する傾向にあります。インターネット上の口コミや評判が全て正しいとは限らないため、誤った情報の訂正や削除依頼をしましょう。誤った情報に対して不安を感じている場合は、解決できるように丁寧に説明することで信頼を得られます。
内定者の状況を把握
内定者の状況を把握し、内定者ごとに適切な内定者フォローをすることも大切です。
可能であれば他社の選考状況の確認や、自社の志望度の確認をしましょう。志望度が低く複数社から内定を得ている場合、内定者フォローをしても辞退する可能性が高いと判断できます。
また、公務員を希望していないか、留年の可能性はないかなども確認することをおすすめします。公務員を志望する場合、合格すると一般企業の内定は断る可能性が高いためです。内定を受ける可能性の低い内定者にアプローチするより、可能性の高い内定者に重きを置いた方が内定辞退の確率を下げられます。
自社のビジョンや課題を共有する
選考時に自社のビジョンを伝えましょう。どのようなビジョンがあり、どのような人材を求めているのかを明確にすることで、ミスマッチによる内定辞退を防げます。
また、悪い面は課題と捉えることや、新卒が近い将来どのような仕事をするかをイメージさせることも大切です。新卒の必要性を説明して、自社に必要な人材であることをアピールしましょう。
新卒から内定辞退の申し出があったときは
新卒から内定辞退の申し出があった際は、無碍にするのではなく次に活かす取り組みが大切です。ここからは、新卒から内定辞退の申し出があった際に取る行動をご紹介します。
理由の聞き取り
内定辞退の申し出があった際は、内定辞退をした理由の確認をしましょう。なぜなら、原因を把握することで適切な対処ができるためです。
例えば、「他社に魅力を感じたため」と回答した場合は、自社の魅力や強みを再確認して、適切にアピールできているかを見直しましょう。
内定者フォローの施策はさまざまあるものの、原因に基づいた施策をしなければ効果は限定的です。
採用プロセスの見直し
新卒の辞退の理由によっては、採用活動を見直すことで内定辞退が減る可能性もあります。
例えば、面接官の印象が悪いことに対してマイナスイメージを持たれていた場合は、親しみやすい面接官への変更が有効です。キャリアプランが不明瞭なことに不安を持っている場合は、将来のビジョンを具体的に説明しましょう。
つながりを持ち続ける
内定辞退をされたからといって、関係を断つことは避けましょう。なぜなら、内定辞退者が中途採用の候補者になる可能性があるためです。
内定辞退の申し出があった際には、丁寧な対応を心がけましょう。相手を応援する趣旨の言葉をかけたり、自社を受けたことへの感謝を伝えたりなど、よい関係を築くことで、将来再度志望してもらえる可能性が高まります。
理由の聞き出しも丁寧に行い、内定辞退者とつながりを持ち続けられるようにしましょう。
まとめ
時間や費用、労力をかけて内定者を決めたにも関わらず、内定辞退をされることは避けたい事態です。
新卒が内定辞退をする際には何かしらの理由があります。自社に原因がある場合は改善することで内定辞退を防げます。
内定辞退の申し出があった際は理由を確認し、今後の採用業務に活かしましょう。
内定辞退を防ぐ対策は複数ありますが、ABABAの利用がおすすめです。新卒スカウトサービスABABAは、他社の最終選考まで進んだ優秀な人材にのみアプローチできます。その他、以下の特徴があり内定辞退の可能性を減らせます。
◆ABABAの特徴
| ・内定承諾率が業界No.1の67% ・学生の情報が可視化されているため、自社に合う人材にのみアプローチできる ・最終面接まで進んだ優秀な人材に絞って人材を探せるため、選考フローを削減できて内定者フォローに時間を使える |
以下の資料でも、内定辞退を防ぐ9つの施策を紹介しています。ご紹介した施策と併せて、以下の施策の実施もおすすめです。
内定を辞退する理由の把握に努めて、最適な施策を実施し、内定辞退を減らしましょう。
この記事の監修者
杉原 航輝(株式会社ABABA 執行役員)
新卒・中途採用領域を中心に、法人向けの採用支援や採用コンサルティングを経験。ダイレクトリクルーティングを含む採用戦略設計から実行支援まで携わる。
また、新卒採用における内定者フォローや採用定着を目的とした施策設計・立ち上げにも従事。
2023年より株式会社ABABAに参画し、執行役員としてマーケティングおよびインサイドセールスを管掌。











