就活における売り手市場とは?売り手市場のメリット・デメリットや採用のポイントを解説!
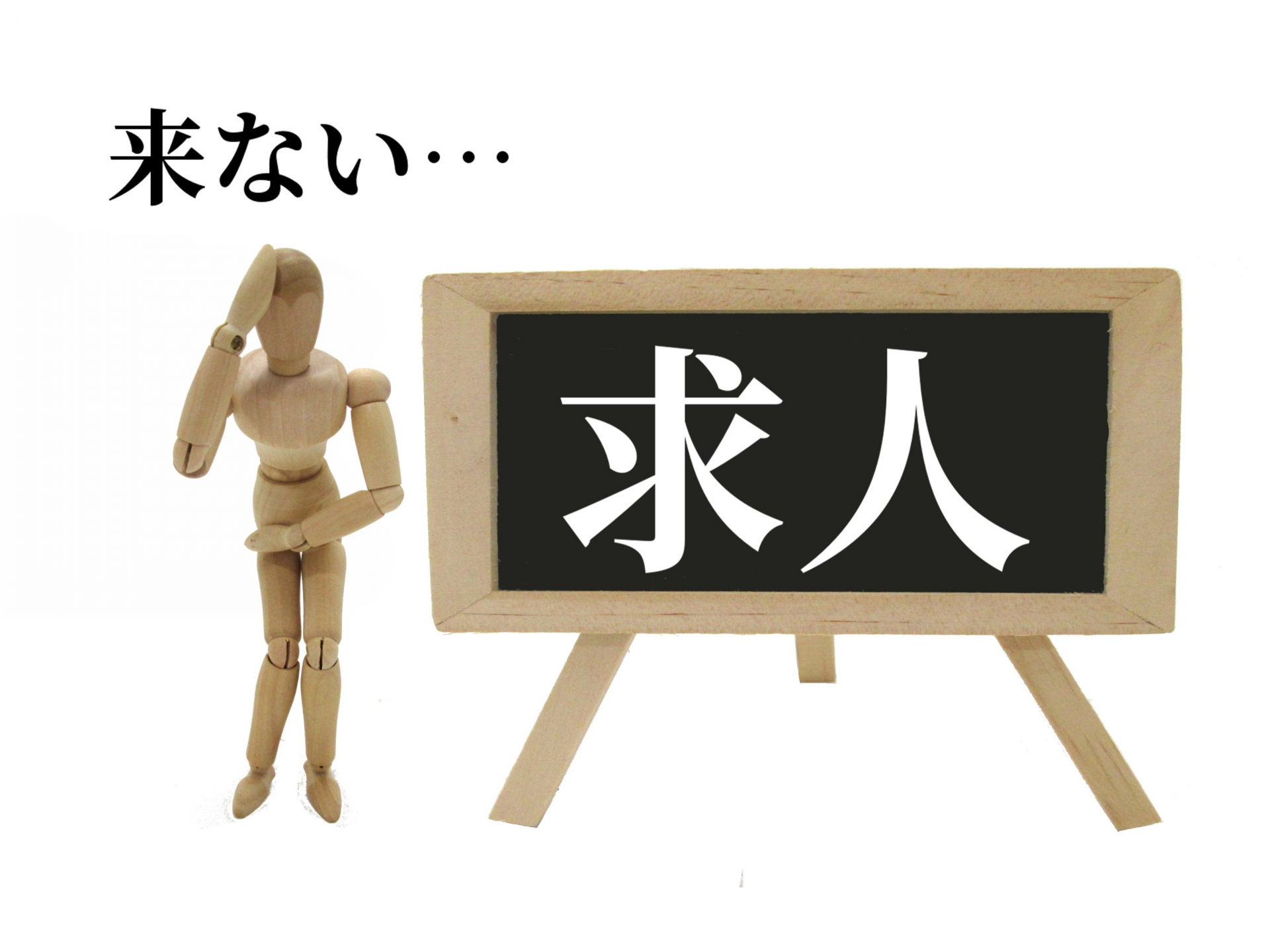
就活において売り手市場という状況が注目されています。
売り手市場とは、企業の求人数に対して、就職を希望する人の数が不足している状態を指します。このため、企業は優秀な人材を採用するために、より魅力的な待遇を提示したり、積極的にアプローチをする傾向にあるでしょう。
就活生にとっては、自分に合った企業を選べるチャンスが増え、選択肢が広がる点が特徴です。この記事では、売り手市場のメリット・デメリットや、企業が採用活動で押さえるとよいポイントについて解説します。
「ABABA」はAIを活用して、ニーズに応じた採用プロセスで、効率的な採用活動を実現します。状況に応じた対応が可能で、企業が求める優秀な人材確保の支援ができるでしょう。
就活における売り手市場とは?
就活における売り手市場とは、企業の求人数に対して、就職を希望する人の数が不足している状態を指します。このような市場では、企業が採用を進めるために、より魅力的な条件を整備し、積極的な就活生へのアプローチが一般的です。
企業側は、優れた人材を獲得するため、待遇やキャリアパスの提示などに力を入れる傾向があります。一方で、就活生にとっては選択肢が広がり、自分の希望に近い企業を見つけやすいため、就活がスムーズに進む状況です。
売り手市場の特徴として、企業側の競争が激化し、就活生にとっては有利な立場であることが挙げられます。
買い手市場との違いは?
買い手市場とは、就活生の数が企業の採用人数を上回る状況のことを指します。この状況では、企業側が自社に必要な人材を慎重に見極め、採用選考が厳しくなる点が特徴です。
就活生側は、希望する企業への入社が難しく、自分の希望通りの職場探しが困難になるでしょう。
買い手市場では、企業が優れた人材を選び抜ける反面、就活生にとっては競争が激しく、条件に合う職場に就職する難易度が上がります。
売り手市場と比較して、就活生にとっては不利な環境といえます。
売り手市場は景気に連動
売り手市場は、景気と密接に関係しています。経済活動が活発になれば企業の人材需要が高まり、労働市場は売り手優位の状況に傾く傾向です。
売り手市場や買い手市場は、求職者一人に対してどれだけの求人があるかを示す指標である有効求人倍率によって判断します。有効求人倍率が1倍以上であれば売り手市場、1倍未満であれば買い手市場です。
「完全失業率、有効求人倍率」を参照すると、2008年のリーマンショック後のような景気後退期は買い手市場、2010年代後半の日本の緩やかな経済成長期には売り手市場に転換しました。
ただし売り手市場であっても、状況は業界や職種によって異なります。労働市場変化を理解し、人事戦略を考えるようにしましょう。
売り手市場の現状
日本の新卒採用市場は売り手市場が続いており、企業の採用意欲が高い状態です。売り手市場である理由は、以下の3つが挙げられます。
- 少子高齢化による労働力不足
- パンデミックからの経済活動の再開
- 企業のデジタル化推進に伴う新たな人材需要の拡大
リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、大卒求人倍率は2012年卒の1.23倍から2019年卒には1.83倍まで上昇し、2025年卒では1.75倍でした。
売り手市場の傾向は短期の景気変動に左右される可能性があるものの、今後も続く可能性が高いでしょう。
人材確保の競争が激化する中で、売り手市場を念頭においた採用戦略が新卒採用の成功の鍵を握ります。
従業員規模・業種別の動向
新卒採用市場動向は、企業規模や業種ごとに大きな差が見られます。中小企業では売り手市場が拡大し、大企業では買い手市場です。
業種別では流通・建設業で売り手市場が見られ、金融・サービス業では買い手市場が続いています。
具体的にはリクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査(2025年卒)」を参照すると、以下の通りです。
- 300人未満の企業で6.50倍、300〜999人で1.60倍と上昇傾向。5000人以上の大企業では0.34倍と低下傾向。
- 流通業は16.21倍、建設業は9.35倍と高水準。金融業は0.23倍、サービス・情報業は0.36倍と低い水準。
新卒採用担当者は、自社の規模や業種に応じた新卒採用計画を考える必要があるでしょう。人手不足が続く業界では魅力的な採用条件をしたり、早くから学生に向けたアプローチをしたりすることが重要です。
売り手市場のメリット
企業にとって売り手市場は、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、売り手市場のメリットを2つ紹介します。
待遇改善が進む
売り手市場は企業にとって待遇改善を促し、長期の組織力強化につながるよい機会です。売り手市場では学生が企業を選ぶ立場に立つため、企業は採用条件を見直さざるを得ません。
たとえば初任給の引き上げや住宅手当の拡充、リモートワーク制度を導入し、学生にアピールする企業は増加しています。待遇改善は採用活動だけでなく、今働いている従業員のモチベーション向上や定着率向上にもつながります。
売り手市場は、企業にとって待遇改善のきっかけとなるでしょう。新卒採用を成功させるだけでなく、長期的視点での組織力強化に貢献するメリットがあるといえます。
競合分析が充実する
売り手市場において人材獲得競争に打ち勝つため、競合他社の動向をより深く分析し、自社の採用戦略を見直す機会が増えます。
他社がどのように学生にアピールするのか、効果のある採用手法は何かを分析しなければ、学生に選ばれる企業になることは困難です。他社の採用戦略やトレンドを分析したうえで、自社の強みを最大限に活かす工夫が求められます。
たとえば競合他社の採用サイトを分析した結果、SNSを活用して学生の関心を引いていることが分かれば、自社でも採用活動や仕事内容などを紹介するSNSの開設を検討してみるとよいでしょう。その際に単に他社の真似をするのではなく、自社らしさを伝えられる投稿を目指す姿勢が大切です。
他社と比較して自社の強みは何か、どのようにアピールすれば求職者に伝わるのかを明確にすることで、採用成功率を高められます。
売り手市場のデメリット
売り手市場は、企業側にとっては求人が埋まりやすく、採用活動が円滑に進む一方で、いくつかのデメリットも存在します。売り手市場の特性を理解した上で、企業はどのように人材を確保するかを工夫する必要があるでしょう。
ここでは、売り手市場のデメリットについて解説します。
求人が埋もれやすい
売り手市場では多くの企業が人材確保に向けて積極的に採用活動を行うため、求人情報が急増します。その結果、ハローワークや求人サイトには多くの募集が掲載され、個々の求人が埋もれやすい状況といえます。
知名度の低い企業や、中小企業は大手企業の求人に埋もれてしまい、学生の目に留まりにくい点が課題です。さらに、情報が多すぎることで、就活生がどの企業を選べばよいか迷い、結果的に応募を見送るケースも増加するでしょう。
応募者が集まりにくい
売り手市場では、求人数が増えることで、就活生が分散する懸念もあります。
特に、売り手市場が進んでいるエリアや特定の職種においては、企業が期待する数の応募者を集めることが難しい場合もあるでしょう。
就活生の選ぶ余地が多く、自社の求人に応募してもらえる可能性が低くなるため、応募者が自社に興味を持ってもらえるような魅力的な求人内容や、企業の特徴アピールが重要です。
優秀な人材を確保しにくい
売り手市場では、求職者に対して求人が豊富にあり、特に優秀な人材に対する競争が激化するでしょう。企業が優秀な人材を確保するためには、多くの応募者から最適な候補者を選びます。しかし、応募者数が限られている場合、限られた候補者から選ばざるを得ないため、選択肢が狭まります。
経験豊富で即戦力となる人材ほど、多くの企業からスカウトメールやオファーが届いているため、なかなか狙い通りの人材から応募を獲得できない状況になりやすいでしょう。
面接辞退が発生しやすい
売り手市場では、就活生が複数の企業に同時に応募し、選考を並行して進めることが一般的です。その結果、就活生は複数の内定を得る可能性が高まり、より条件のよい企業を優先して選考を進めます。
このため、優先度の低い企業の面接は辞退されることが多く、採用担当者にとっては選考の途中で候補者が離脱するリスクも高まります。特に、他社の内定承諾期限が迫っている場合や、求職者のスケジュールが過密になると、辞退の可能性がさらに増すでしょう。
内定辞退が発生しやすい
売り手市場では、求職者が複数の企業に応募し、内定を複数獲得する場合が一般的です。そのため、企業が内定を出しても、求職者が他社の内定を選ぶケースが増え、内定辞退が発生する可能性も高まります。特に、給与や福利厚生、企業の成長性などを比較し、より条件のよい企業を選択する傾向が強まります。
内定辞退を防ぐには、面接時に企業の魅力をしっかり伝え、求職者に自社で働く意義への理解が重要です。また、就活生に対して、企業側からの丁寧なサポートやフォローアップによって、内定辞退を減らせる場合もあるでしょう。
入社後の早期退社につながりやすい
売り手市場では、入社後の早期退職リスクが高くなります。
優秀な求職者を逃がしたくない企業が採用ハードルを下げたり内定を急いで出したりする傾向があるため、求職者が十分な自己分析や企業研究を怠ったまま入社を決めてしまうケースが少なくありません。
新卒者が企業からの早期内定に喜び内定を承諾したものの、働いてみると業務内容が想像と異なって退職を検討する例は多く聞かれます。
ミスマッチは求職者側の準備不足だけでなく、企業が採用人数を揃えることを優先し、適性を見極めないまま内定を出していることも一因です。
早期退社は採用コストの増加や人材育成の機会損失を招き、企業にとっても大きな痛手です。企業は求職者との丁寧なコミュニケーションを通じて、早期退職を防ぐ努力が求められます。
売り手市場で採用を行う際のポイント
売り手市場では、求職者が多くの企業からオファーを受けるため、採用活動において差別化が必要です。企業が積極的にアプローチし、優秀な人材を確保するためには、いくつかのポイントがあります。
ここでは、売り手市場で採用を行う際のポイントについて紹介します。
採用対象のペルソナを明確にする
新卒採用において使われる「ペルソナ」という言葉の意味は、「採用したい学生の人物像」のことです。
ペルソナを設定する際は、年齢・学歴・サークル・趣味など、採用要件だけでは見られない細かい項目まで具体的に想定しなくてはなりません。
それらを設定することによって、求める人材の認識が明確化され、採用するべき学生へのアプローチ方法を割り出しやすくなります。
採用活動の際は求める人材像を明確にし、それに合致する訴求内容を考えるとよいでしょう。
採用フローを見直す
採用フローを最適化し短縮することも、採用活動を効率的に進めるために重要です。
また、採用フローを見直すと、学生の選考離脱を防止しやすくなります。
面接の回数が多すぎたり、選考と選考の間が空きすぎたりすると、学生からので企業の優先順位が下がり、辞退されやすくなります。
また、全ての面接を対面で行う場合、地方からの応募が減りやすくなるというデメリットがあるでしょう。
面接フローを考え直したり、オンラインでの選考を導入したりすることで、学生の離脱を防げます。
学生のニーズ・トレンドを把握する
売り手市場で採用を行う際に重要なポイントとして、学生が求める条件や価値観の変化を敏感に捉えることが挙げられます。社会情勢やテクノロジーの進化、働き方の多様化など、学生の関心を引くような採用戦略を立てることが成功の鍵です。
学生のニーズやトレンドは、時代の流れとともに変化します。たとえばAIの発展によって、人間にしかできない仕事を探す学生が増えてきました。さらにハラスメント問題への意識が高まり、企業のコンプライアンスや職場環境の透明性を重視する求職者が大半です。
学生のニーズやトレンドを的確に把握し、柔軟に対応する姿勢が企業に求められています。
複数の採用手法を併用する
近年の採用活動では、1つの就活サイトに情報を登録して待つだけでは優秀な人材を取り逃しやすいといえます。
優秀な人材を企業に集めるためには、求める人材像に合わせて、複数のサービスを使ったり、採用手法を使い分けたりすることがおすすめです。
従来の就活サイトからの応募数が増えないときは、スカウトメールや人材紹介などを活用しましょう。
スカウトメールは企業が直接求職者に求人を届けられるため、企業の情報を見てもらいやすいといえます。
攻めの採用活動を行う
売り手市場では、企業が消極的な姿勢を取ると、他社に先を越されてしまうリスクが高まります。そのため、積極的にアプローチする「攻めの採用活動」が重要です。
スカウト型の採用手法、特にダイレクトリクルーティングを活用することで、特定の専攻分野や経験を持つ学生に直接アプローチできるため、効率的に優秀な人材を確保できます。この方法は、競争が激しい売り手市場において、差別化を図る有力な手段となるでしょう。
自社の認知度を高めて母集団を形成する
現代の大学生はデジタルネイティブであり、インターネットやSNSを活用した情報発信が不可欠です。企業は自社のホームページやSNSを活用し、求職者に向けた情報を積極的に発信することで、認知度を高める必要があります。
イベントやセミナーを開催し、学生に直接企業の魅力を伝える活動も効果的です。自社を認知していない潜在層の学生にも、新卒採用を実施している企業であると知ってもらい、母集団の形成が求められます。
学生に早期にアプローチする
優秀な人材を確保するには、学生に早期にアプローチする積極的な姿勢が不可欠です。近年、就職活動の開始時期が早まる傾向にあり、他の企業と同じ従来のタイミングで動いても魅力ある学生と出会えない可能性があります。
たとえば大学3年生の夏以前から学生と接点を増やし、インターンシップを開催して接点を増やすとよいでしょう。文部科学省の「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」にて、2025年度卒業生からインターン参加者への選考開始が3年生の春休みに前倒しできるようになりました。早期にアプローチすることの重要性が高まっています。
企業は従来の採用スケジュールを見直し、学生との接点を早めに持てるように工夫する姿勢が求められます。
学生に接触する機会を増やす
学生と企業が接点を持つ機会を増やすことも、採用活動の質改善に効果的です。
企業と学生が接点を持つ機会としてこれまで広く用いられてきたものとして、インターンシップがあります。
インターンシップ以外にも会社見学会や面談などを行い、学生との接触機会を増やすことで、幅広い人材にリーチできるようになるでしょう。
また、インターンシップや説明会をオンラインで参加できるようにすると、地方在住の学生にも接触しやすくなります。
採用・面接担当者がスキルアップを図る
近年の就活市場では、企業の学生と同様に選ばれる立場であるという意識が重要です。
一方的に学生を選べばよいという考えはやめ、採用担当者は「自社も学生に選考される立場である」ということを理解しましょう。
採用担当者や面接担当者の印象が悪いと、選考中や内定後に辞退される可能性が高くなります。
候補者によい印象を持ってもらえるようにするために、採用担当者・面接担当者のスキルアップを図るとよいでしょう。
働きやすい職場環境を整備する
売り手市場では、求職者が企業を選ぶ際、給与や福利厚生だけでなく、働きやすい職場環境が重要なポイントです。
企業は、福利厚生・職場の雰囲気・ワークライフバランスなどに配慮した環境づくりを進めることで、従業員の満足度を向上させ、就活生にとって魅力的な選択肢となり得ます。柔軟な勤務体系やリモートワークなど、働きやすさにこだわることが、売り手市場での採用活動成功には不可欠です。
社内のコミュニケーションやチームワークの向上も、職場環境の改善には重要です。
売り手市場での採用成功例
売り手市場において、企業は優秀な人材を確保するためにどのような戦略を取れば良いのでしょうか。
求職者にとって選択肢が多い環境では、従来の採用手法だけでは十分な成果を上げるのが難しくなります。ここでは、売り手市場の中で採用に成功した企業の具体的な事例を紹介し、どのような施策が効果的だったのかを解説します。
自社サイトに採用者向けのブログを設置して成功(東京都F社)
自社サイトから採用者向けの情報を見られるようにして、採用活動に活かした例があります。
東京都のF社は、自社サイトにおいてブログコンテンツを用いた情報発信に力を入れている企業です。
採用活動においてもブログを活用し、就活生からの企業認知度を高めることに成功しました。
ブログに掲載するインタビューでは、ポジションやキャリアを問わずさまざまな社員を取り上げており、多様な働き方ができることのアピールも兼ねています。
オウンドメディアによる自社情報の発信で成功(東京都M社)
東京都のM社は急激なスピードで成長している企業である一方で、新たな人材と企業文化とのミスマッチが多いことが課題でした。
そこでM社は、入社後ギャップを減らして適切な人材を採用できるようにするために、オウンドメディア採用に力を入れました。
オウンドメディアは、採用活動を問わず情報発信に効果的です。
M社は採用ブランディング用オウンドメディアを立ち上げることで、企業の透明化・認知度向上に役立てました。
また、採用や組織文化発信の専門チームを設けることで、候補者との接点強化も行いました。
地域における企業ブランディングで成功(岩手県D社)
岩手県D社は、地域社会との結びつきを深めることで企業の認知度を高め、多様な人材獲得に成功しました。地元での花火大会の復活や地域開発プロジェクトなどのイベントに積極的に参加することで、「地域に貢献する企業」としてのブランドを確立しました。
地元に貢献したい求職者の多くは、「自分の働きが地域に貢献できる」と実感できる企業を探しています。D社は地域住民のニーズに応えながら事業を発展させることで、求職者からの注目度を高めることに成功しました。
ユニークな選考・採用手法で成功(神奈川県K社)
神奈川県K社は独自の選考プロセスを設けて、企業の魅力をアピールすることに成功しました。
同社では選考スピードよりも面接の質を優先し、企業文化への共感や創造性を重視しています。具体的には新卒の通年採用を実施し、学歴や卒業時期を問わず、誰でもエントリーできる仕組みを整えました。その結果、通常の採用スケジュールでは獲得できない多様な人材の獲得に成功しています。
さらに応募者のゲームスキルを評価した採用やインターネットの検索結果を活用した採用企画を展開し、アプローチが難しい人材を獲得し、早期退職率0を達成しています。
企業の強みを活かした柔軟な発想で、自社に共感する人材を獲得した採用成功例といえるでしょう。
SNSによる採用広報で成功(千葉県S社)
千葉県のS社は、採用活動にSNSを用いることでそれまでの課題を解決しました。
S社では従来、ハローワークや求人サイトを用いて採用活動を行ってたものの、若手層の採用が振るいませんでした。
課題解決のためには企業のイメージそのものを変えて若者に伝える必要があるとして導入されたのが、SNSを用いた採用戦略です。
SNSを用いた広報と「パンフレットデザインや説明会での装飾を若者向けにする」「若手向けの会社説明を行う」などの施策を行った結果、近年は若者からの応募が増加しています。
まとめ
売り手市場において採用を成功させるには、企業が積極的にアプローチし、自社の魅力を的確に伝えることが重要です。
企業は攻めの採用活動を行い、ダイレクトリクルーティングなどを活用して優秀な人材に直接アプローチする必要があります。自社の認知度を高めるため、SNSやホームページを活用し、セミナーやイベントを通じて母集団の形成も大切です。さらに、就活生に選ばれるためには、福利厚生の充実や働きやすい環境の整備も不可欠です。
売り手市場では、企業の積極的な姿勢と他社との差別化が求められます。
このような課題解消には、「ABABA」がおすすめです。
◆ABABAの特徴
| ・最終面接に進んだ学生を対象としたスカウト機能で、採用活動を加速できる ・直接アプローチによって、他社より早く優秀な求職者を確保できる ・企業のニーズに応じた採用プロセスで、効率的な採用活動ができる |
ABABAは多くの就活生に利用され、企業と学生のマッチングを支援しています。他社の最終選考を通過した学生に直接アプローチできるスカウト機能は、優秀な人材を効率的に確保する有力な手段となるでしょう。
また、競合企業の最終面接合格者に特化した新たな採用手法も有効です。
お役立ち資料では、採用成功を加速させる具体的な戦略や成功事例を詳しく解説していますので、ぜひご活用ください。
>>(無料)「競合の最終面接通過者のみを集める 新卒採用の新常識」を見てみる
この記事の監修者
杉原 航輝(株式会社ABABA 執行役員)
新卒・中途採用領域を中心に、法人向けの採用支援や採用コンサルティングを経験。ダイレクトリクルーティングを含む採用戦略設計から実行支援まで携わる。
また、新卒採用における内定者フォローや採用定着を目的とした施策設計・立ち上げにも従事。
2023年より株式会社ABABAに参画し、執行役員としてマーケティングおよびインサイドセールスを管掌。











